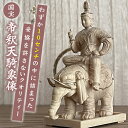|
「表外読み」 私たちが日常生活で使用する漢字の目安となるものに、「常用漢字表」というものがあります。これは内閣によって定められており、字数にして2136字が登録されています。その常用漢字表には、漢字だけでなく読み方も記されているのですが、中には、常用漢字表に記載のない読み方をする漢字もあります。その常用漢字表に載っていない読み方のことを、「表外読み」といいます。 |
Q1. 燥ぐ

①はしゃぐ
②さわぐ
③そよぐ
Q2. 途

①みち
②あぜみち
③こみち
Q3. 罷る

①まかる
②うけたまわる
③はやる
↓
↓
↓
↓
↓
↓
Q1. 燥ぐ
正解①はしゃぐ

②さわぐ…闹ぐ/骚ぐ/閙ぐ/鬧ぐ/噪ぐ/鬨ぐ/騒ぐ/擾ぐ/躁ぐ/譟ぐ/騷ぐ
③そよぐ…战ぐ/戦ぐ/嫋ぐ/戰ぐ/嬝ぐ
Q2. 途
正解①みち

②あぜみち…阡/町/甼/陌
③こみち…径/迳/徑/逕/蹊
Q3. 罷る
正解①まかる

②うけたまわる…承る/奉る
③はやる…逸る/逸る/逸る
したっけ。
















![シュウメイギク(秋明菊):桃花一重3号ポット* 2株セット[宿根草] シュウメイギク(秋明菊):桃花一重3号ポット* 2株セット[宿根草]](https://m.media-amazon.com/images/I/61jaJsCf1mL._SL500_.jpg)




![面白いほど幸せになる漢字の本【電子書籍】[ ひすい こたろう ] 面白いほど幸せになる漢字の本【電子書籍】[ ひすい こたろう ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4717/2000002944717.jpg?_ex=128x128)